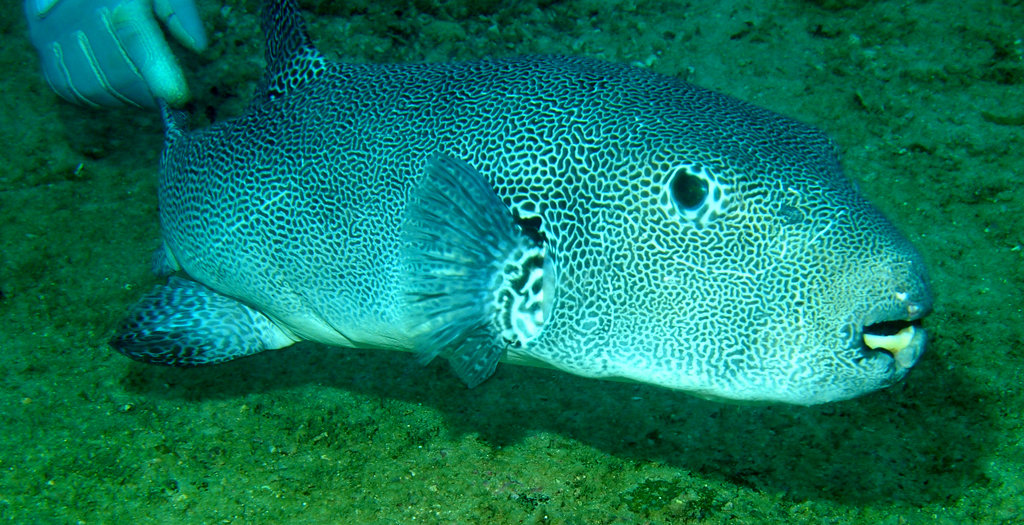今年も9月の第3土曜日がやってきました。高校は8月の下旬、中学は9月の第1日曜と脱ゆとり教育のための授業時間数の確保のためかどんどん早まってきています。受験などあまり気にしない地方都市の小学校でさえ授業時間数確保のためきゅうきゅうとした年間行事予定になっているようです。今年は天気の心配を全くせずに当日朝を迎えました。
運動会の話題といっても何回か書いているうちに内容がだぶってしまいそうですので、今回は自分の運動会の競技の思い出にふれてみましょう。「何が一番思い出に残っているか?」と自問自答してみました。「やっぱり組体操かなあ?」当時の組体操は今の子供たちよりもう少し難度が高かったような気がします。別に今の子供たちがひ弱だと言っているわけではありません。あと全校皆で一斉に踊ったフォークダンス。あれは少し恥ずかしながらの遠い想い出です。今の小学校の運動会でフォークダンスがないのはなぜでしょうか?他の小学校ではあるのでしょうか?皆さんの子供さんの小学校ではありましたか?文科省の指導要綱の改定のためにフォークダンスが姿を消したようですが、定かでありません。先日、35年ぶりに再会した同級生とのんだとき、私が富田東小学校の校庭の風景写真をこのブログに出しているのを見て「まだ、あの当時の上り棒があのまま残って使われているなんてメチャクチャ懐かしかったよ」というコメントをいただき、そういうことを聞くと「ブログをやってよかったなあ」と嬉しくなってしまいます。
さて今回も無事小学校の運動会が終わり、残すところあと2回です。勿論、中学や高校に行っても運動会はありますが、運動会観戦をして親として一番心に残り一緒に楽しめるのは小学校だと思います。なぜなら子供が小学1年のときの運動会はドキドキものだったのを思い出しませんか?それから学年が上がるに連れて少しずつたくましくなって徒競走も速くなっていきませんでしたか?そして最高学年では今まで上級生にお世話にしてもらってようやくいろいろなことができていた我が子が低学年のお世話をするようになって子供の成長を6年がかりで見届けたこと思い出してみてください。親子ともどもとってもいい想い出になっているはずです。小学4年生の晴れ姿は今年も午前は仕事で観ることができませんでしたが、午後の競技は観戦できました。我が子以外の他のお子さんやご両親ましてや祖父母の皆さんもいい笑顔で観戦しています。「子供は社会の宝」だとよく言われますが、まさにその通りだと運動会を観戦しながら感じている自分がいます。今回の運動会でうちの子供も親バカながら少しは大きくなりたくましくなったなあと思いながら観ています。先々週も書きましたが、「この中からもしかしたら東京オリンピックに出て金メダルをとる子供がいるかも」という可能性を秘めた夢と希望を抱きながら、全国の運動会で観戦している両親がたくさんいるに違いないと思っています。
最後の写真は運動会当日の早朝6時に花火と同時に校門が開いて〝雪崩のごとく一斉に走り出す一瞬〟でさすがにぶれました。清々しいとはいえない残暑の残る秋の1日でした。